わたしは1回だけムラヴィンスキーの実演を聴いたことがある。1979年の6月だったと思うが、彼が日本を訪れた最後の機会だった筈だ。場所は横浜(神奈川県民ホール)、プログラムはベートーヴェンの田園交響曲とヴァーグナーの管弦楽曲(森のささやき、ヴァルキューレの騎行、それともう1曲何か)で、アンコールはあったかな、ローエングリン第3幕の前奏曲だったかも知れない。何と最前列真ん中で、目の前に1st.ヴァイオリンの第2プルトがあり、右を見上げると長身のムラヴィンスキー、という席だった。オーケストラはもちろんレニングラード・フィル。
当時のわたしは「ムラヴィンスキーなんだから、やっぱりチャイコフスキーかショスタコーヴィチでも聴きたい」と思っていた。何と言ってもわたしのムラヴィンスキー初体験は、今は無き新世界レーベルの『革命』で、背筋を電撃が走るような強烈な体験だったのだから。
しかし、その『田園』もまた強烈な体験だった。鶴のように真っ直ぐに立ったムラヴィンスキーがバトンを振り下ろした瞬間に、聴き慣れた筈のヘ長調の旋律が、ピンと張りつめた鋼鉄のワイヤーのように響いたことは今でも忘れられない。あの親しみやすい音楽は殆どなく、終始、全く乱れをみせない禁欲的なアンサンブルが繰り広げられるのだった。
後半のヴァーグナーでは、鋼鉄のアンサンブルにはますます磨きがかかり、機甲師団の進軍のようなヴァルキューレが終わると、聴衆の興奮も頂点に達した。楽団員がすべて退場した後も指揮者は何度もステージに呼び出され、拍手を受けた。このときのムラヴィンスキーの表情も忘れ得ぬもので、彼は両手を前で組み合わせ、ニコニコ笑いながらガッツポーズをしてみせた。口をへの字に結び、オーケストラを睨みつける写真ばかりのムラヴィンスキーとは全く異なるイメージが鮮烈だった。
彼が西側に初めて演奏旅行を行ったときの、聴衆の驚愕はどのようだったのか。天下のドイツグラモフォンが、1950年代後半から60年代前にかけてのレニングラード・フィルのツアーの機会をとらえ、2度までもチャイコフスキーの録音を残したことが西側音楽界のフィーバーぶりを示しているような気がする。そういえば1978年のヴィーンでのライブ盤も、何と4枚組のセットで発売されたっけ。
今にして思えば、あの『田園』はやっぱり特殊な演奏だったのだろうと思う。CDで彼のブラームスの交響曲第2番を聴いたときも「ちょっと、向いてないんぢゃないか」などと思ったものだが。おそらく、今の自分があの演奏を聴くと、似たような感想を持つかも知れない。
しかし、やっぱりムラヴィンスキーはもの凄いと思うのだ。余人をもって代え難い強烈な個性であり、それを実現する鉄壁のアンサンブルがあり、すさまじい程の緊張感にとらえられたときの衝撃は他では味わえない。だから、時々はCD棚から彼の録音を取り出して、聴いてみたいと思うのである。
ムラヴィンスキー讃
 東越谷音楽通信
東越谷音楽通信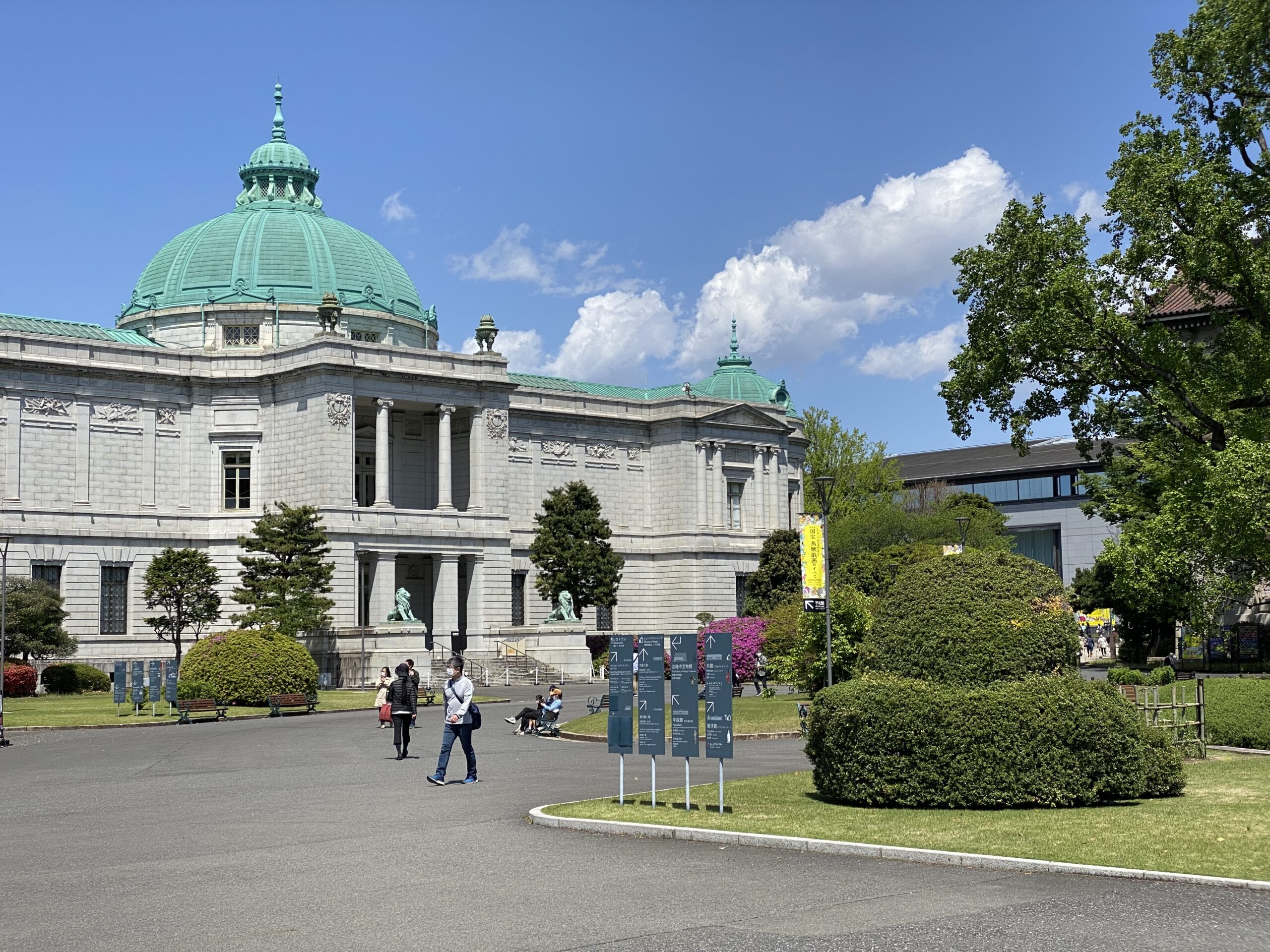
コメント